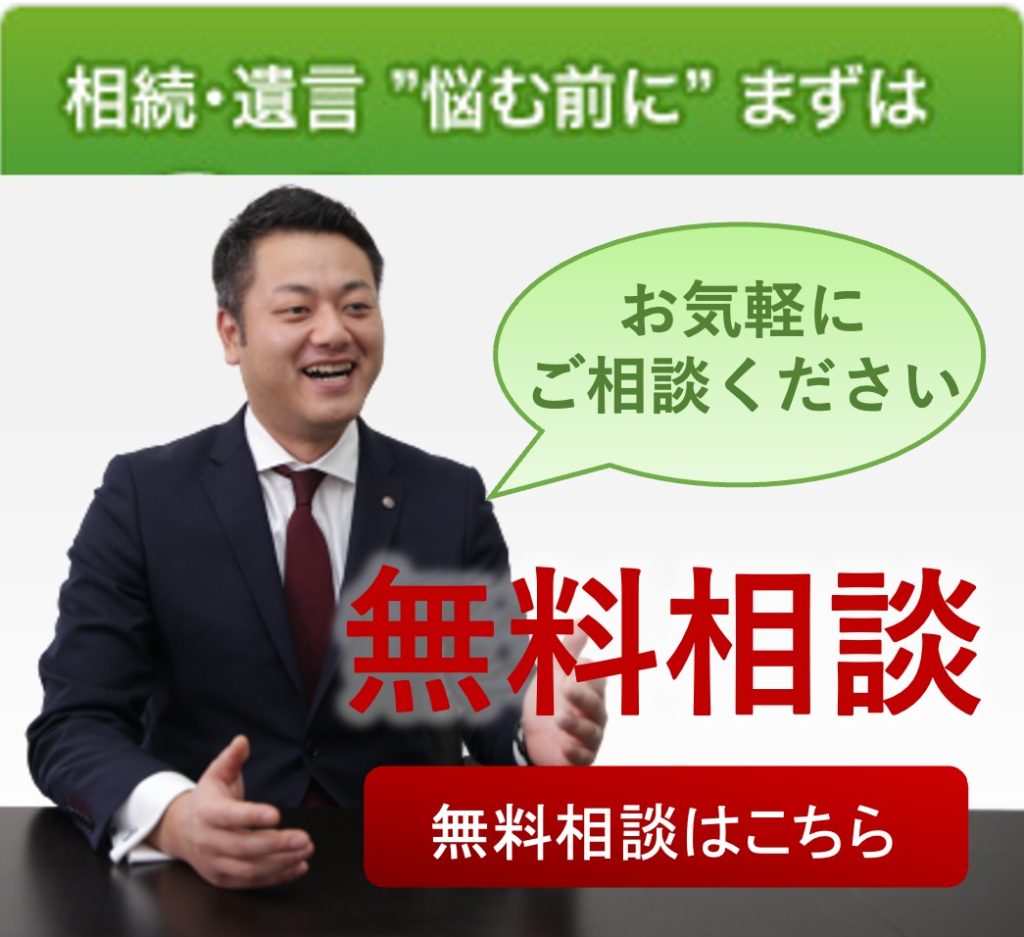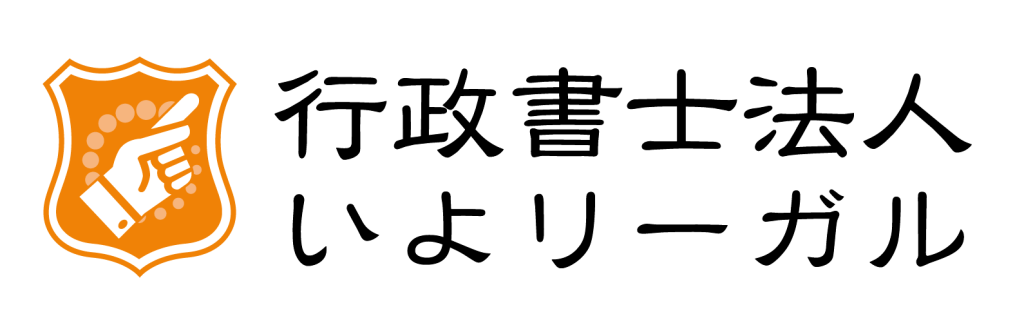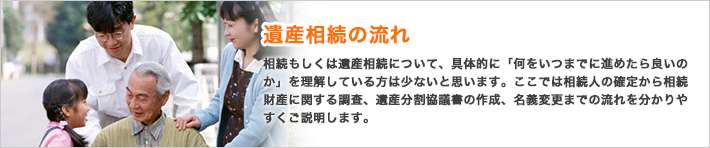
遺産相続の事例
事例1
質問
父が亡くなった際に、金融機関に多額の借金があることが分かりました。相続人は私一人なのですが、私には父の借金を支払う義務があるのでしょうか?
回答
相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内であれば、裁判所で「相続放棄の手続き」が可能です。この手続きにより、お父様の借金を支払う必要は無くなります。
ただし手続きを取らないと、お父様の財産を借金も含めて全て相続したとみなされるため、あなたに借金を支払う義務が生じます。お父様の資産内容が明らかでなく、相続放棄の判断がつかない場合は、家庭裁判所に期限の伸長申立てをすることができます。
資産の全容が把握できず、相続放棄を選択する可能性がある場合は、伸長申立てをお勧めします。
事例2
質問
父が亡くなり、預貯金と不動産が残されました。相続人は私と兄の2人なのですが、遺書はありません。遺産分割については話し合って決めるつもりなのですが、今後、どのような手続が必要になりますか?
回答
2人で話し合い(この話し合いを「遺産分割協議」と言います)、遺産分割について合意できたら「遺産分割協議書」を作成します。不動産については「遺産分割協議書」などを法務局に提出し、登記移転手続きを行い、預貯金は銀行などで払戻しを受けます。また遺産の額によっては相続税を納める必要があります。
面倒な手続きですが、行政書士が「相続コーディネーター」を務める「愛媛あんしん相続相談所」にご相談いただければ、手続きを代行いたします。お気軽にご相談ください。
事例3
質問
父が亡くなり、次男である私を含む子供3人が相続人になりました。父と同居していた長男は「遺産は全て長男に渡す」という内容の遺言書を持ち出し、「ほかの者には遺産を一切渡さない」と主張しています。しかし長男のことを嫌っていた父が、このような遺言書を残すとは考えにくく、偽造の可能性が拭い切れません。また、長男は父にどれだけの遺産があったのかも明らかにしてくれません。どうしたら良いのでしょうか?
回答
まずは「遺言書が有効かどうか」を判定しなければなりません。当時のお父様の精神状態・健康状態を主治医に確認し、遺言書が作成できたかを見極めるほか、遺言書の指紋鑑定や筆跡鑑定により、科学的に判定することができます。
次に「遺産内容の確認」です。以前とは違い、相続人は銀行に対し、相続人全員の同意が無くとも、単独で預金取引履歴の開示を請求できます。預金の履歴を開示してもらい、お金の流れを追跡することで、資産形成や運用状況がある程度明らかになるでしょう。また名寄帳や登記簿謄本、共同担保目録、固定資産税の課税状況、火災保険の加入状況、確定申告、相続税申告状況などを調査すれば、不動産の保有状況も判明する場合があります。
同様に生命保険の受取状況や出資金の返還、自動車の生前贈与などについても、任意調査や弁護士会の文書照会、裁判所の調査嘱託などにより調査可能です。
調査内容によっては複雑な手続きが必要ですが、行政書士が「相続コーディネーター」を務める「愛媛あんしん相続相談所」にご相談いただければ、手続きを代行いたします。お気軽にご相談ください。
事例4
質問
私には認知症の母がいるのですが、最近、兄が母名義だった自宅を自分名義に書き換え、母と同居を始めました。兄には多額の借金があり、「自宅は母から贈与を受けた」と言っていますが、認知症の母に確認することはできません。贈与自体が無効だと思いますが、どうしたら良いのでしょうか?また、母には1500万円の預貯金があり、このお金で母を施設に入れようと思っているのですが可能でしょうか?母の死亡後の相続でも兄と揉めそうで不安です。
回答
認知症になった段階での贈与は無効です。お母様の主治医に話を聞き、「贈与を決意できるような精神状態では無かった」ことを確認してください。また、法務局で登記移転の原因証書たる贈与契約書の写真を取らせてもらい、筆跡鑑定をするなどして贈与の無効を主張しましょう。
お母様を施設に入所させるためには、「成年後見制度」を利用します。本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人(保佐人・補助人)が決定される制度で、「法定後見」とも言います。あなたやご兄弟、あるいは第三者の弁護士や司法書士を成年後見人に選任してもらい、その人が本人に代わって各種契約などを行います。
成年後見人選任後に本人が死亡した場合は、財産を管理している成年後見人から、相続人が管理財産を引き継ぎます。ただし分割内容について揉めているような場合には、成年後見人は財産を引き渡せなくなるので、一旦、財産管理人の選任を裁判所に申し立て、その財産管理人に財産を引き渡してもらいます。遺産分割の調停を申し立て、取り分について解決できた後に、ようやく財産を受け取ることができるようになります。
事例5
質問
今年で85歳になる私には、少しですが土地と預貯金があります。3人の子供たちには相続のことで揉めて欲しくありません。今から何かできることはないでしょうか?また、今のところ身体は健康なのですが、最近、物忘れがひどく、認知症への不安が増しています。いざというときのために、何かしておくべきことはありませんか?
回答
相続財産に土地や建物などが含まれるケースでは、遺産分割協議がもつれることが珍しくありません。今回のようなケースでは、公証役場で「公正証書遺言」を作成し、予め相続内容を決めておくことをお勧めします。遺言書は自分で作成することもできますが、形式が厳密に定められており、ちょっとした記載漏れなどで無効になることがあります。後々の揉め事を未然に防ぐためにも、「公正証書遺言」を作成するのが無難です。
将来の認知症対策としては、判断能力のあるうちに後見人を選任しておく「任意後見」が有効です。通常は最も信頼できる親族あるいは弁護士などの第三者を「成年後見人」に指定し、公証役場で公正証書を作成して、財産管理を任せる「任意後見契約」を結びます。契約をしておかないと、いざというときに信頼できない親族などが成年後見人になり、勝手に財産などを使われてしまう可能性が出てきます。