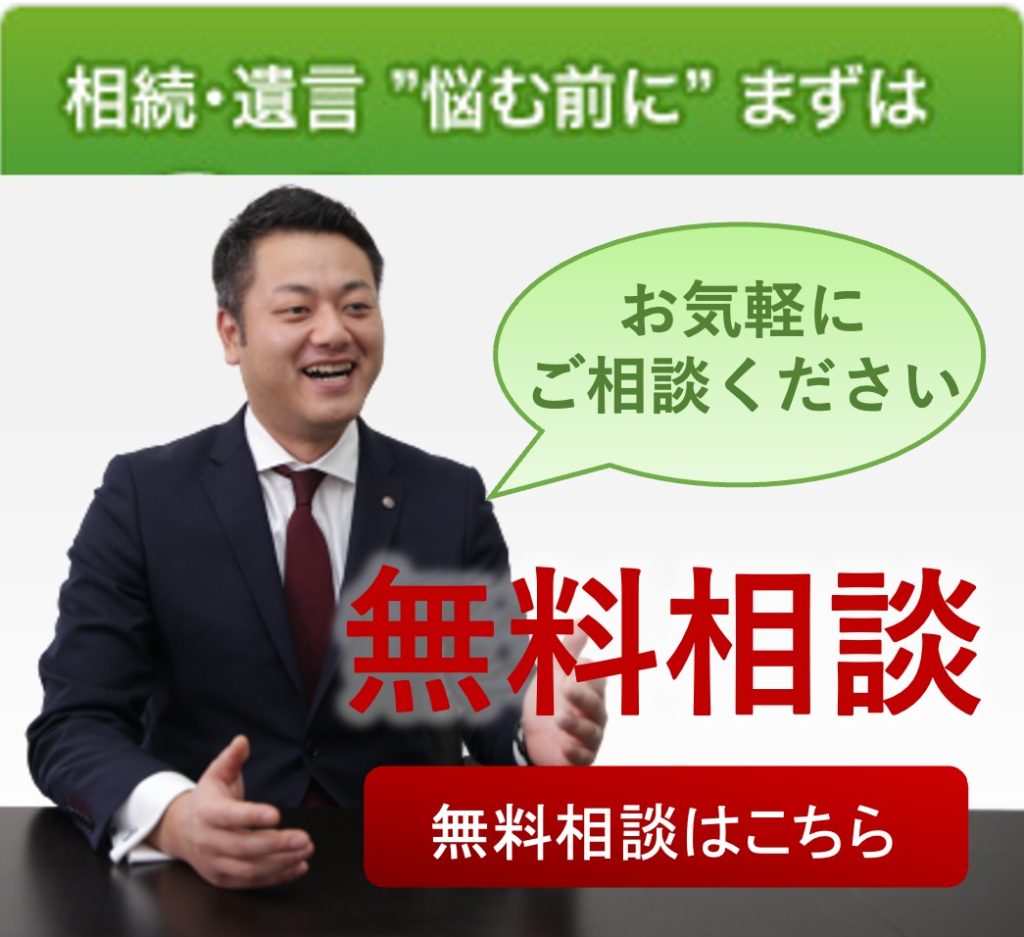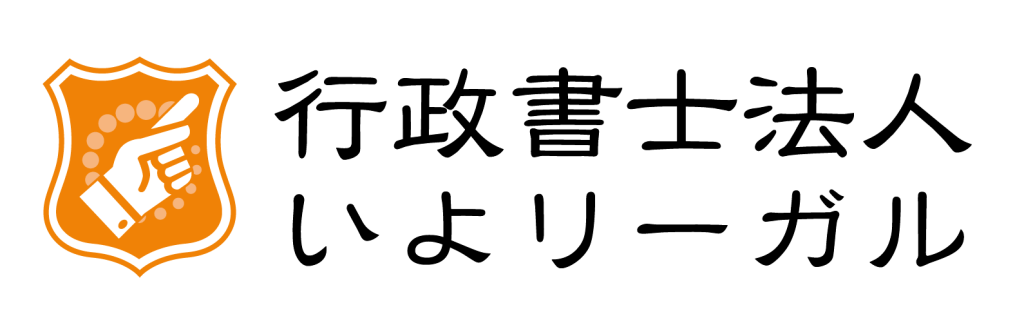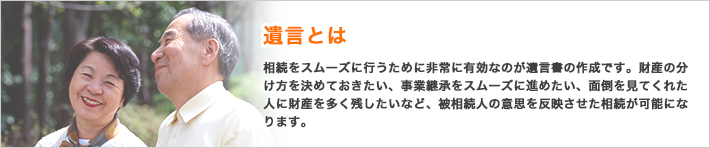
遺言の執行
遺言の執行とは、遺言者の死後、遺言の内容を実現するための一連の手続きのことです。遺言の執行にあたっては、信頼できる人物を「遺言執行者」に指定できます。遺言執行者は遺言書による指定が必要で、生前の取り決めでは、遺言執行者として認められません。また、執行内容が複雑になる可能性があるときは、複数の執行者を指定できます。遺言執行者に指定できる人に制限はありませんが、指定された人には辞退も認められているため、適切な人物を指定するには、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
遺言の執行には、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、執行者がいなければ手間がかかることも多くありますが、必ずしも指定しなくてはならないものではありません。
遺言の執行の流れ
① 財産目録の作成
遺言者の財産を証明する登記簿、権利書などを揃え、財産目録を作成し、相続人に提示します。
②遺産の分配
遺言に示されている、それぞれの相続人の相続割合に沿って、実際に遺産を分配します。また、登記申請や金銭の取り立てを行います。
③不法占有の対処
相続財産を不法に占有する者がいる場合は、明け渡しや移転を求めます。
④遺贈の執行
遺言書に相続人以外に財産を遺贈することが記載されている場合は、指示された配分に従い、遺産を譲渡します。
⑤ 認知の届出
遺言書に指定の人物に対する認知の希望が記載されている場合は、執行者が遺言の謄本とともに認知の届出を行います
⑥ 相続廃除
虐待や財産の不当処分、異性問題や犯罪行為など、相続人の素行に問題がある場合は、その相続人に対し「相続権の剥奪」を申し立てることができます。相続廃除はよほどのことがない限り認められませんが、このような制度があることは知っていた方がよいでしょう。
執行人は相続人に対し、遺言の執行が完了するまで全ての財産の持ち出しを差し止める権利が認められています。一方で執行人は相続人に対し、報告の義務を追っています。相続人は遺言の執行が完了した際、執行の内容に応じた報酬を執行者に支払います。報酬額は家庭裁判所が定めることもできますし、遺言の中で指定することもできます。